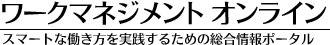まずは仕事の見える化からはじめよう
DXに取り組んでいない企業はいないと言えるほど、業界を問わずDXへの関心は高い。突然「DXに取り組め」というお題を与えられ、どこから取り組んだらいいのかわからず、まずは情報収集、社内で検討中という企画管理部門の方は多い。検索すれば、さまざまな「成功の秘訣」が出てくる。デジタル人材の育成、開発の内製化、アジャイルアプローチ、トップ経営層のコミットメント、などなど。どれも一朝一夕には進められない話ばかりだ。
 そこで、本記事では「まずはデジタル化からはじめる」ことを提言したい。デジタル化という言葉はわかりにくいので、「仕事の見える化」と言い換えても良い。こう言うと「いや、DXとはデジタル化だけのことではないと聞いた」「仕事の見える化はDXとは呼べないのではないか」と思う方もいらっしゃるだろう。たしかに「デジタル技術を導入し、業務を効率化するだけではDXとは呼べない」のは事実だ。だが、あえて「それでもデジタル技術による仕事の見える化からはじめるのが良い」とお伝えしたい。
そこで、本記事では「まずはデジタル化からはじめる」ことを提言したい。デジタル化という言葉はわかりにくいので、「仕事の見える化」と言い換えても良い。こう言うと「いや、DXとはデジタル化だけのことではないと聞いた」「仕事の見える化はDXとは呼べないのではないか」と思う方もいらっしゃるだろう。たしかに「デジタル技術を導入し、業務を効率化するだけではDXとは呼べない」のは事実だ。だが、あえて「それでもデジタル技術による仕事の見える化からはじめるのが良い」とお伝えしたい。
DXとは、その言葉があらわすとおり、トランスフォーメーション、つまり変革である。事業変革、企業変革と考えれば、それが極めてむずかしいことだとわかる。一説には、7割の変革プロジェクトは失敗に終わっていると言われている。
だからこそ、わかりやすいところからはじめる必要がある。「仕事の見える化」は、経営層からも社員からもわかりやすい。そして、仕事が見える化できると、業務効率が高まるだけでなく、利益率の向上につながり、さらにはビジネスモデルの変革にまでつながることを解説していきたい。
日本企業特有の仕事の進め方がDXを阻んでいる
ボストン・コンサルティング・グループ初代日本代表のジェイムズ・アベグレンが、著書『日本的経営』で日本企業の経営の特徴を1. 終身雇用、2. 年功序列、3. 企業内組合にあると論じたのは1958年のことである。以降60年以上にわたりこの特徴が維持されてきたわけだが、特に終身雇用と年功序列は、日本企業で働く私たちの日々の仕事の進め方に大きく影響を与えてきた。
新卒で入社した会社で長く働くことは暗黙の前提となっており、上司・先輩もまたその会社で長く仕事をしているため当然その仕事に詳しく、わからないことは「聞けばすぐにわかる」環境が長く続いた。職場では上司や先輩を「見て学ぶ」ことが多く、「長い期間をかけて経験を積む」ことが認められている。また、長く勤務するなかで、経験を積むために社内異動や転勤も多く、そのたびに「仕事(職種)が変わるのは当然」と受け止められている。
これらの特徴をひとことでまとめるなら、「仕事が定義されていない」と言えるだろう。昨今話題のジョブ型雇用をきっかけに、海外の企業においてはジョブ・ディスクリプション(職務定義書)があると聞いた方も多いだろう。これはまさに仕事を定義する文書である。この仕事はこういう内容で、こんなスキルが求められ、このような成果物をつくり、こんな基準で評価します、と決める。終身雇用と年功序列が前提ではない場合、仕事を定義しないとそもそも人を採用できないのである。また、社内異動の際も、この公開された内容をもとに面談がおこなわれ、異動の可否が判断される。
さて、これがDXとどのように関係するかといえば、定義されていない仕事はデジタル化できないのである。コンピューターの基本的な仕組みは、インプットとアウトプットが決まった仕事(タスク)を処理することである。こういうインプット(入力)があったら、こういう処理をして、こういうアウトプット(出力)をする。これが事前に定義されているから、さまざまなタスクを高速で自動的に処理できるわけだ。仕事が定義されていなければ、当然デジタル化はできない。ここに、日本企業がデジタル化やDXを進める上で大きな遅れを取りやすい構造的な理由がある。
デジタル化とは仕事を定義すること
デジタル化とは「仕事を定義すること」なのである。本来の意味でのDX、デジタルを活用したビジネスモデル変革を進めるにも、まずは仕事が定義できなければはじまらないのだ。仕事が定義できていれば、それをシステム化・デジタル化することはそれほどむずかしくない。
ところが、多くの日本企業では、仕事を定義する必要がなかった。だから、ほとんどの人は仕事を定義したことがない。もちろん、生産工程を設計したり、エンジニアリング(プラント、機械、ITなど分野を問わず)に携わってきた人からすれば、タスクやプロセスを定義することは日常茶飯事だ。だが、そういった人たちですら、会社の中で当然のようにおこなわれている業務、たとえば営業活動や取引先とのやり取り、部門内や他部署との連携といった業務を定義せよと言われると、とまどうだろう。実は、仕事を定義するには高度な分析スキルと経験が求められる。専門的なスキルを持つ人であっても、自分が経験したことがない業務を分析し定義するのは時間がかかる。そういったスキルを持つ人が社内にいなければ、外部から調達する必要があり、それにはお金もかかる。また、専門家を雇ったとしても、プロセスの分析や手順のドキュメント化には、非常に多くの労力がかかる。さらに、一度作って終わりではなく、継続的なアップデートが必要になるが、優先度は上がらず滞りがちだ。現場を知っている経営者ほど、ここに予算や専任の担当者を割り振る決断ができない。人材の流動性が低い(離職率も中途入社率も低い)企業では、そもそも〇〇さんに聞けばわかる、という甘えが通じるので、仕事を定義する意欲が湧かない。

業務プロセスの分析や仕事の定義といった業務は、これまで情報システムの開発に合わせておこなわれることが多かった。これは逆に言えば、システム開発の対象にならない仕事については、分析も定義もされないまま放置されてきたということである。製造業であれば生産管理や調達、販売会社であれば受発注については古くからシステム化され、仕事のやり方も効率化されてきた。だが、それ以外の業務については驚くほど非効率なやり方が残っていることが多いのは、これが理由だ。このように、多くの日本企業はホワイトカラーの仕事を定義してこなかったことで、デジタル化が進んでいないのだ。
分析不要、日々の仕事をデジタル化する方法
しかし昨今、業務分析スキルを外部から調達するために高額な費用を支払って「社内の仕事を分析・定義する」というアプローチに大きな変化が出てきた。テクノロジーを活用することでむずかしい業務分析をせずとも、業務が一気にデジタル化されるケースが増えているのだ。わかりやすい例が「カレンダーアプリ」や「ビジネスチャット」である。
OutlookやGoogleカレンダーなどのカレンダーアプリは、「いつ、だれが、どこで何をしている」というアナログな情報をデジタル化した。ビジネスチャットは、日々職場で交わされる何気ないやり取り(コミュニケーション)をデジタル化した。デジタル化されたことによって、検索できる、その場にいなくても確認できる、チームで共有できる、振り返りや分析ができるというデジタルの強みによって、業務効率は格段に向上したはずだ。
ビジネスチャットを例にあげてみよう。メールでやり取りするほどでもない仕事上のコミュニケーションは、これまで電話や対面の会話、ホワイトボードや付箋などアナログな方法でやり取りされていた。アナログでのコミュニケーションには、あとから検索できない、その場にいないと確認できない、共有できない、という不便さがある。これが、顧客や取引先との「言った言わない」、上司と部下の理解が食い違う、経営層からの大事な伝達が全員に伝わらない、といったことを引き起こしていた。

ビジネスチャットは、この不便さを一気に解消し、日々のコミュニケーションをデジタル化した。ビジネスチャットを導入した企業では、これまでアナログな方法でやり取りされていた仕事のコミュニケーションが、すべてデジタル化される。高度な分析や特別な作業はなにもせず、ただ日々のやり取りをすべてグループチャットでおこなうだけだ。隣の人に話しかけていたら、その場かぎりで消えてしまう話も、グループチャットでやり取りすることでデジタルな記録として残る。日々の仕事をしているだけで、暗黙知だった最前線の生情報が記録として残っていく。これにより、「組織としての経験」が蓄積され、加速的に組織力が向上していく。「チームのグループチャットの盛り上がり度合いとチームの成績は明確に比例している」と断言する経営者もいるほどだ。
コミュニケーションの次は仕事そのものをデジタル化
コミュニケーションがデジタル化されたら、次は仕事そのものをデジタル化していく。仕事を「アウトプットを出すこと」と考えると、なんらかのインプットがあり、処理をして、アウトプットをつくるというプロセスに分解できる。このような仕事の流れ、つまり業務プロセスをデジタル化していくのだ。だれが何をやって、だれにどう渡すのか。次の人は何をチェックするのか。抜け漏れがあれば手戻りが発生することもある。では、どんなときに手戻りが発生し、何を修正するのか。こういったことをデジタル化していくのだ。
例えば、次のような2つのWebサイトがあったとき、皆さんが使いやすいと感じるのは、どちらだろうか。
- 入力項目に沿って、ステップ・バイ・ステップで進んでいき、エラーがあったらどこを直せばいいかわかりやすく提示してくれるWebサイト
- 入力項目が自由記入ばかりで、つまずくとすぐに「お問い合わせください」と出てくるWebサイト
言うまでもなく前者の方が使いやすいだろう。前者は仕事が定義された状態であり、後者は仕事が定義されていない状態である。「わからないことがあったら聞いて」という上司や先輩は親切なようでいて、実は単に仕事を定義していないだけなのだ。この状態では、経験が浅い社員はひとりで仕事を進めづらい上に、社内で不要なやり取りが発生する。期限はいつなのか、そもそもアウトプットは何なのかを上司に確認する、そのために必要な作業は何なのかを先輩に聞く、必要な参考資料をその都度探す、といった「仕事のための仕事」が大量に発生する。Asana社による調査*では、日本で働くナレッジワーカーがこういった「仕事のための仕事」に費やす時間は、実に勤務時間の61%におよぶという。

ここで、日々の仕事そのもの、つまりAさんが処理し、Bさんが次の作業をし、Cさんが確認するといった仕事の流れをツール上でおこなうとどうなるか。ビジネスチャットが日々のコミュニケーションをデジタル化したように、ワークフロー**は日々の仕事の流れをデジタル化してくれる。デジタル化されれば、検索できる、その場にいなくても確認できる、共有できる、振り返りや分析ができる、といったデジタルの強みを活かして、仕事のやり方を改善できる。しかも、専門家の力を借りることなく、現場の社員が自分たちの仕事を改善していけるのだ。
* 出典:『日本版「仕事の解剖学」インデックス 2022』
** 日本では「ワークフロー」という言葉は、なぜか「申請・決裁」と同じ意味で使われるようになっているが、本来の意味は言葉のとおり「仕事の流れ」「業務プロセス」である。
見える化は、利益率の向上やビジネスモデル変革につながる
日々の仕事の流れ、それも事業の根幹を支えるような業務が見える化・デジタル化されると、何が起こるのだろうか。直接的には、その業務が効率化される。これは容易に想像できるだろう。だが、インパクトはそれだけではない。
業務のデジタル化は、利益率の改善や新規取引先の開拓という形で、事業成長につながる。さらには、ビジネスモデルの変革(本来の意味でのDX)につなげることもできるのだ。具体例を見ていこう。
利益率の改善
エンジニアリングやシステム開発など、顧客や案件ごとにプロジェクトを組成していくタイプの業種では、個々のプロジェクトの採算管理が企業の利益率に直結する。また各プロジェクトは、顧客からの厳しい要求により、多くの場合は利益率がそれほど高くない。たったひとつのプロジェクトが赤字化するだけで、10プロジェクトの黒字が吹き飛ぶこともある世界だ。
水事業を中心とする環境衛生施設のエンジニアリング事業者 水ingエンジニアリングはまさにこのようなプロジェクトを数多く手掛けており、各プロジェクトの採算管理はきわめて重要であった。しかし、顧客の予算が厳格化されるにつれ、担当者が抱えるプロジェクトの数は増え続け、管理者が担当者の負荷を把握することも、適切な指示を出すことも困難になっていった。担当者もまた多くの仕事に忙殺され、適切に優先順位をつけることができず、また抜け漏れも発生しやすくなっていた。管理者も担当者も全体像が見えず、指示漏れ・確認漏れが増えていけば、手戻りも発生しやすくなる。プロジェクト型の仕事において、手戻りは大きな損失を生む。これらは一見すると些細なことに見えるが、分析の結果、指示や確認の抜け漏れの積み重ねが、事業の収益性を圧迫していることが明らかになった。
水ingエンジニアリングにとって、エンジニアリングフロー(基幹業務の流れ)がAsanaによって見える化・デジタル化されたことのインパクトは大きかった。顧客の厳しい要求に応えつつ、各プロジェクトで収益を確保できるようになったのだ。
- 各担当者がやるべき仕事を見失わなくなった。
- 管理者が、メンバーの仕事量を把握し、タイムリーに的確な指示が出せるようになった。
- 管理職や同僚が、各自どんな仕事を抱え、何に困っているかが詳しくわかるようになった。
ひとつひとつは小さな改善に見えるかもしれない。だが、逆に言えばこれができていないだけで、事業の利益率は悪化する。決して無視はできない。
水ingエンジニアリング株式会社の関連記事はこちら
大手取引先の開拓
暗黙の了解で仕事が進められてしまう環境は、事業の成長を阻害する。なぜなら、同じ品質(製品品質だけでなく、プロセスの安定性や納期の正確性を含む業務品質)でサービスを提供できないと、新規顧客の信頼を得ることはむずかしいからだ。中小企業が新規の顧客を獲得するのがむずかしく、馴染みの顧客に依存しがちなのはこれが理由だ。
海外競合との価格競争を受け、2次請け3次請けの仕事を脱し、事業構造を大きく変えようと、買収・合併を繰り返しながら成長してきたテック長沢は、まさにこの悩みを抱えていた。これまでのような暗黙のやり方では大手の取引先には通用しない。一次請けとして大手顧客から仕事を直接受注するためには、受発注のやり取りや品質担保の体制、納期を遵守するためのプロセスなど、これまでとは違う仕事のやり方が必要だった。
買収・合併により組織と人員が拡大し、仕事のやり方が複雑化・煩雑化するなか、Asanaを使って仕事を見える化したことで、テック長沢は大きく変化した。
- 何度も催促が必要だったことがすぐに進むようになり、顧客への回答が迅速になった。
- 定例会議の時間が半分になった。
- 半日かけていた仕事が1時間で終わるようになった。

仕事の見える化は、品質マネジメントの国際規格取得を後押しした。実は取得に向けて2年かけて準備していたにもかかわらず、合格が危ぶまれていたのだが、仕事が見える化したことで社内プロジェクトがスムーズに進行するようになり、無事に取得できた。業務品質の高さ・安定性にお墨付きがついたことで、大手顧客との取引拡大が見込まれる。
株式会社テック長沢の導入事例はこちら
ビジネスモデルの変革
事業の根幹となる業務がデジタル化されると、これまでは不可能だった事業が可能になる。いわゆるビジネスモデルの変革だ。
そろばん、手切りの食券、手書きのノートで運営していた老舗飲食店ゑびやは、店舗運営にまつわるさまざまな業務を自動化していくことで、7年で売上4.8倍に急成長するというめざましい成果を上げた。しかし、これはあくまでも事業拡大の話。ゑびやはそこに留まらず、新しいビジネスモデルをつくり上げた。
自社向けに開発したシステムや関連ツールを外販する事業を開始したのだ。来客予測、顧客の属性分析、販促の効果測定、店舗の可視化、クロスセル分析、アンケート自動収集。こういったシステムは、店舗を運営する事業者にとって価値が高い一方で、自社で開発するのはスキル面でもコスト面でも非常にハードルが高い。子会社EBILABを通じて、システムだけでなく、自社で培った店舗運営のノウハウも含めて提供することで、顧客を獲得している。伊勢の老舗飲食店が、店舗運営事業者向けのITシステム販売という新しいビジネスモデルをつくれたのは、事業の根幹となる店舗運営の業務プロセスと関連するデータをすべてデジタル化したからこそ実現できたことだ。
事業の根幹となる業務をデジタル化できれば、これまではリソース面やコスト面の制約から不可能だった事業が可能になる例は他にもある。
大手・中堅企業向けの事業をおこなっている企業の多くは、営業人員を数多く抱えている。提案から受注までの期間が長かったり、既存取引を踏まえた提案が必要だったりと、人が対応しなければならない部分が大きいからだ。それらの業務は通常見える化されておらず、部や課の中で独自ノウハウとして伝承されている。これらの業務をデジタル化すると、どうなるか。顧客からの問い合わせ内容や、それに対する社内調整を経た回答や提案、顧客からの発注と社内での受注処理の流れ。こういった仕事の流れをデジタル化できると、ある程度のパターンが作れるようになる。
パターンが作れれば、これまで大手・中堅向けにしか提供できなかった自社事業を、中小企業向けに提供できる可能性がある。顧客からの問い合わせを定型フォームで受け付け、その後の処理をある程度自動化してしまうのだ。こうすれば、営業人員を割くことなく(つまり大きなコストを掛けることなく)、新しい市場を開拓できる。顧客の要望すべてをパターン化するのはむずかしいと諦めず、6割の完成度でもいいので試してみる。中小企業向けの市場の特性がつかめれば、問い合わせフォームを選択式にしたり、提供する製品・サービスを絞ったりすることで、さらに自動化を進められる可能性が見えてくる。顧客が発注できるところまで自動化できれば、セルフ・サービス化の完成だ。業務のデジタル化を進めることで、大手・中堅企業に対して人によるカスタマイズした営業活動とはまったく異なる、中小企業向けのセルフ・サービス型事業がつくれる。
老舗飲食店ゑびやの導入事例はこちら
DXという難題への第一歩は仕事のデジタル化から
メールやチャットの導入によりコミュニケーションがデジタル化されたことで、情報が検索しやすく、共有しやすくなった。これからは、仕事そのもの、つまり業務プロセスをデジタル化していくことが求められている。ここまで見てきたように、仕事の見える化・デジタル化によって、利益率の向上、新規顧客の開拓、新たなビジネスモデルによる新規事業創出も可能になる。これらはまさにDXに対して経営層が期待している成果である。
まずは仕事の見える化からスタートすることで、小さな成功を積み重ねることができる。数ある変革(トランスフォメーション)の要諦のなかに、「短期的成果(スモールサクセス)を生み出す」ことがある。DXという大きなテーマに取り組むにあたり、仕事の見える化というわかりやすい活動からはじめ、経営層や社員の賛同を得ながら、大きな成果につなげていってほしい。

萩原 雅裕
Prodotto合同会社 代表
/Asanaアンバサダー
萩原 雅裕 / Prodotto合同会社 代表
NTTデータ、ベイン・アンド・カンパニー、日本マイクロソフト、Microsoft Corporation(本社)を経て、創業メンバーとしてワークスモバイルジャパン株式会社に参画。法人向けコミュニケーションツール「LINE WORKS」の立ち上げに携わり、導入社数30万社超、ARR78億円(2021年現在)までの成長に貢献。プロダクト責任者、マーケティング責任者、カスタマーサクセス責任者、戦略担当役員などを歴任。現在は、SaaSグロース支援、B2Bマーケティング支援、経営アドバイザリーサービスを提供。働き方改革やビジネスコミュニケーションに関する講演、テレビ・ラジオ出演、新聞・雑誌掲載の実績多数。
慶応義塾大学卒業、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院(MBA)修了。趣味は、筋トレ、キャンプ、積ん読。
- カテゴリ:
- DX(デジタルトランスフォーメーション)